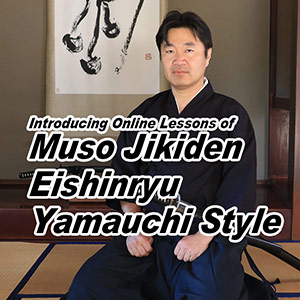主祭神:
八意思兼命 (やごころおもいかねのみこと)
知知夫彦命 (ちちぶひこのみこと)
天之御中主神 (あめのみなかぬしのかみ)
秩父宮雍仁親王 (ちちぶのみややすひとしんのう)
創建:第十代崇神天皇の御代 紀元前87年
主な神事:例祭 12月3日
秩父神社は、秩父地方の総社である。秩父三社(秩父神社・三峯神社・宝登山神社)の一つ。
秩父神社の創建は、第十代崇神天皇の御代に知知夫国の初代国造に任命された八意思兼命の十世の子孫である知知夫彦命が、祖神を祀った事に始まる。2000年以上の歴史を誇る、秩父の総鎮守として現在に至る。
中世以降は仏化し、関東武士の源流、平良文を祖とする秩父平氏が奉じる妙見信仰と習合し秩父妙見宮として栄えた。明治の神仏分離により秩父神社に戻る。現在の社殿は1590年徳川家康によって建てられた。埼玉県の有形文化財に指定されている。
秩父 夜祭
日本三大曳山祭の一つでもあり数少ない国の「重要有形・無形民俗文化財」に指定されている。
例祭は「秩父夜祭」としても知られる。優雅な神代神楽、勇壮な屋台囃子、絢爛豪華な笠鉾・屋台の曳き回し、盛大な花火と毎年20万人が訪れる秩父の冬の風物詩である。妙高信仰とは古代バビロニアに始まり、仏教と共に伝来したものが、平安時代に献灯をもってする北辰際として都で流行したものが、秩父に招来したとされる。
さらに風土の伝記である、武甲山の男神と秩父神社の女神が一年に一度の逢瀬の物語も伝える秩父の風土を伝える郷土祭りでもある。
オフィシャルホームページhttp://www.chichibu-jinja.or.jp/
(参照:オフィシャル情報)